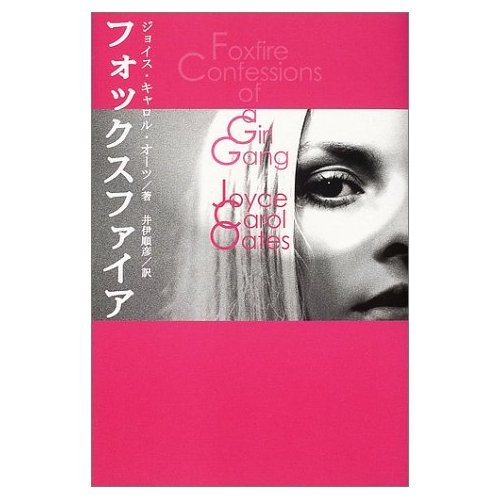1950年代、オンタリオ州。地元の公立高校に通う少女マディはある夜、自室の窓を同級生であるレッグズが叩くところに遭遇する。彼女たちはやがてメンバーを増やしながら「フォックスファイア」という少女だけのギャングを結成し、男性からの暴力や支配に抗うための破壊活動を開始する。しかし、盗車での“はちゃめちゃドライブ”でレッグズが矯正院に送られたことをきっかけにフォックスファイアの絆は揺らぎだし、郊外のボロ屋での共同生活資金を集めるための「引っ掛け(美人局)」は、やがて取り返しのつかない結末をもたらす。
(ネタバレ感想)
本書は性暴力へのバックラッシュを引き起こす可能性がある。犬もひどい目に遭う。
貧困と暴力が支配する街で、少女たちの多くはネグレクトを受け、頼れる大人は誰もいない。学校でも街でも性暴力の危険にさらされ、尊厳を保つことすら難しい。そういった状況でレッグズは、ジョン・デリンジャーやジェシー・ジェームズといった義賊たち、あるいはプロレタリア革命の思想に共鳴し、少女たちをまとめ上げる。
女子矯正院送りになったレッグズはいちど制度の側に回れば女性すら味方ではないことを悟り、黒人にまで援助の手を広げようとする。しかしメンバーの多くはその“急進”的な考えを受け入れることができない。生活費を稼ぐため、そしてふしだらな男性性への逆襲という目的からはじまった美人局は、やがて資本家の誘拐という破滅的な発想に至る。レッグズを狂信する新入りの少女の引き起こした事態により誘拐は失敗に終わり、フォックスファイアは消滅する。
私の非常に限定された知識から言うならばプロレタリア闘争は女性を排斥しがちであり(共闘すべき労働者すらレッグズに侮蔑的な言葉を投げるように)。決死の覚悟で臨んだ資本家の誘拐も、自立した女性たちの起こした事件ではなく(男性しかいない)労働組合の所業とかギャング団の下部組織であるガールズギャングの仕業と言われるほどである。
そういった状況に立ち向かうためにレッグズと「フォックスファイア」が仕掛けた“闘争”は、あまりにむなしい終わりを迎える。彼女たちが受ける(目をそらすことは許さぬぞという執念で書き込まれた)性被害の数々と釣り合うものではない。
語り手としてこの“真実の書”をものしたマディは誘拐の前にフォックスファイアを追放された人物だが、彼女は一貫して天文学に対する強い関心を持ち、終章では故郷を出て大学を出たのち、天文台の観測員として宇宙を監視している。
語り手としてのマディがいるのは、1990年ごろ。冷戦が終結し、社会主義に対するひとつの夢が潰えたタイミングだろう。語りの時点でのマディが何を思っているのかはわからないが、フォックスファイアにいたときと同じ情熱を持っているわけではない。結婚をして離婚をした。男の下で働いている。レッグズが見たかもしれないというキューバ革命も、マディからしてみればその後キューバがどうなったかを知っている。
それでも彼女は探さずにはいられないのだろう。隕石のように現れる何かを。星に手を掛けるほどの高みに登ることのできる存在を。だからこそ、「情熱」を書き留めようとしたのだろう。